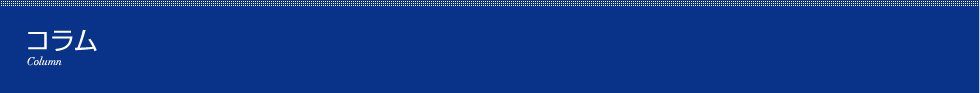
○会計ビックバン;グローバルスタンダードに沿った会計基準へ
投資市場のボーダレス化などによって、日本の会計基準もグローバルスタンダードに合せた見直しが段階的に行なわれています。
2000年3月期の販売用不動産の強制評価減の徹底、連結財務諸表の重視等に始まり、本年度はいよいよ減損会計制度が適用となります。
○減損会計の概要
減損会計の対象となるのは、企業が保有する事業用の固定資産で、具体的には以下のものが挙げられます。
・有形固定資産・・・・土地、建物、工作物、機械装置など
・無形固定資産・・・・借地権、営業権など
・投資その他の資産・・投資用不動産など
上記の資産は、これまでは取得原価主義によって計上・処理をされてきましたが、バブル崩壊以降、時価の下落傾向が続いた結果、時価が帳簿価額を大幅に下回る現象が一般的となり、企業価値の判断材料であるバランスシートの信頼性が薄れてしまいました。その信頼性や透明性の向上のため、事業用の固定資産についても時価評価の考え方を取り入れたのが減損会計です。
つまり、資産の収益見込みが当初の予想を下回ることが確実な場合や、市場価格が大幅に下落した場合等に、資産の帳簿価額を臨時的に減額させる処理(減損処理)を行なわなければなりません。
○減損処置の基本的な流れ
(1) 減損の兆候の有無(兆候無)  減損会計の計上なし 減損会計の計上なし(兆候有) |
|
 |
まず最初に、キャッシュフローを生み出す単位毎(個別又はグルーピング)に、減損の兆候の有無を調査します。具体的には、地価の下落、資産の休止・リストラや経年減価を上回る明らかな減価(滅失・損傷等)などです。減損の兆候のない資産は、この段階で減損処理手続きから除外されます。 |
(2) 減損損失の判定(評価額>帳簿価額)  減損会計の計上なし 減損会計の計上なし(兆候有) |
|
 |
(1)の段階で減損の兆候が認められた場合には、実際に対象資産の評価額を把握することが必要となってきます。実際の評価額と帳簿価額とを比較し、前者が後者を下回る場合には、減損損失が発生していることになります。 |
(3) 減損損失の測定及び計上
(2)の段階で減損損失の発生が認められた資産又は資産グループは、その減価額を測定し、当期の損失として計上します。
具体的には、各資産の帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方を採用)まで減額することになります。
なお、正味売却価額及び使用価値とは以下のとおりです。
・正味売却価額=(資産の時価)-(処分費用)
・使用価値=(ある一定期間の継続的使用によって見込まれるキャッシュフロー)+(使用期間終了後の処分価額)
弊社では、このような減損会計適用にあたり、迅速かつ的確な不動産の評価を行い、できるだけ多くの皆様のニーズに対応できるような体制を整えております。
なお、ご質問、ご相談等がございましたら、弊社までご連絡下さい。
Tel. 03-5213-0123